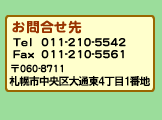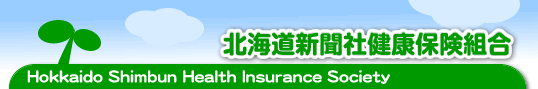|
|
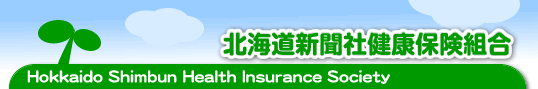 |
| |
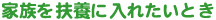
|
|
| 被扶養者(75歳未満)の認定は、主として被保険者によって生計を維持され、被扶養者になる人の年間収入が下記基準額未満で、被保険者の収入の1/2未満であることが基準になります。また、別居の場合は、その家族の年間収入を上回る仕送りをしていることが条件になります。 |
|
|
| |
- 主として被保険者により生計を維持されている次の者。
被保険者の直系尊属・配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹
- 被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されている次の者。
被保険者の三親等内の親族・内縁の配偶者の父母及び子・内縁の配偶者の死亡後引き続き同一世帯に属する父母及び子
|
| |
「主として被保険者により生計を維持されている者」とは、生計費の半分以上を被保険者が継続的、定期的に負担する状態をいう。
「同一世帯に属する」とは、住居と家計の二つを同時に被保険者と一緒にしている状態をいう。 |
| |
認定対象者の年収が被保険者の年収の1/2未満であること。
- <認定対象者の年収基準>
-
60歳未満の場合・・・130万円未満であること。
60歳以上の場合・・・180万円未満であること。
障害年金受給者の場合・・・180万円未満であること。
- <認定対象者が父母等で、配偶者のいる場合の年収基準>
-
父母等の夫婦とも60歳未満の場合・・・208万円未満であること。
父母等の夫婦とも60歳以上の場合・・・288万円未満であること。
父母等の夫婦の一方が60歳未満、もう一方が60歳以上の場合・・・248万円未満であること。
※父母等のどちらかの認定の場合も、配偶者がいる場合、両方の収入の確認をします。 夫婦には強い生計維持関係があるため、扶養認定対象者が、配偶者ではなく被保険者により継続的に生計が維持されているか判断します。
- <別居の場合>
-
認定対象者の年収が、被保険者の援助額より少ないこと。なお、仕送りの方法は、手渡しは認めない。
- <雇用保険の失業給付受給中の場合>
- 失業給付の受給中(待期期間、給付制限期間中を含む)は、認定しない。
|
| |
認定対象者の収入は、課税・非課税を問わず次のものとする。
- 勤労収入(パート、アルバイト収入等を含む)
- 企業年金
- 公的年金(厚生年金、国民年金、共済年金、遺族年金等すべての年金を含む)
- 恩給
- 民間保険等から支給されるすべての年金
- 事業収入(総収入から健保組合の認める経費を引いた収入)
- その他の収入(仕送り、雇用保険の給付金、継続して発生する利子収入・配当収入、その他継続性のある収入等)
- その他認定対象者の生計費に投入できるすべての収入
|
| |
子供の人数にかかわらず、原則として年間収入(被扶養者異動届が提出された日の属する年の前年の年間収入とする)の多い方の被扶養者とする。
夫婦双方の年間収入が同程度の場合は、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする。 |
| |
- 被保険者が資格取得(採用)した場合の被扶養者の認定日は被保険者資格取得日とする。ただし、被保険者資格取得日より10日以内に被扶養者の申請がない場合は、被扶養者異動届(原則として添付書類が完備)の受付日とする。
- 新生児・・・原則として出生日
- その他・・・原則として添付書類が完備し、認定を受けた日
|
| |
- 出生の場合
- 退職した場合
- 戸籍謄本(抄本)または住民票
- 雇用保険受給資格者証(受給終了と記入されているもの 写し)
- 雇用保険受給放棄の場合は、離職票1・離職票2(写し)と誓約書
- 雇用保険未加入の場合は、退社証明書(雇用保険未加入の旨記載しているもの)
- 雇用保険の受給期間を延長する場合は、受給期間延長通知書、離職票1・2 または受給資格者証(写し)と誓約書
- 別居の場合は、送金の控え(直近3ヵ月分)
- その他健保組合が必要とする書類
- パート・アルバイト等で収入が基準額未満の場合
- 戸籍謄本(抄本)または住民票
- 源泉徴収票または給与明細書(直近3ヵ月分)
- 別居の場合は、送金の控え(直近3ヵ月分)
- その他健保組合が必要とする書類
- 結婚の場合
- 戸籍謄本(抄本)または住民票
- 加入していた健康保険の喪失証明書
- その他健保組合が必要とする書類
- 父母の場合
- 戸籍謄本、住民票
- 生活費に投入できるすべての収入の証明書(収入の範囲の項参照)
- 別居の場合は、送金の控え(直近3ヵ月分)
- 他の家族に扶養されていないことを証明する誓約書
- その他健保組合が必要とする書類
- 学生の場合
- 戸籍謄本(抄本)または住民票
- 在学証明書
- その他健保組合が必要とする書類
|
| |
|
「被扶養者異動届」と該当する提出書類を添付して健康保険組合に提出してください。 |
|
|
|